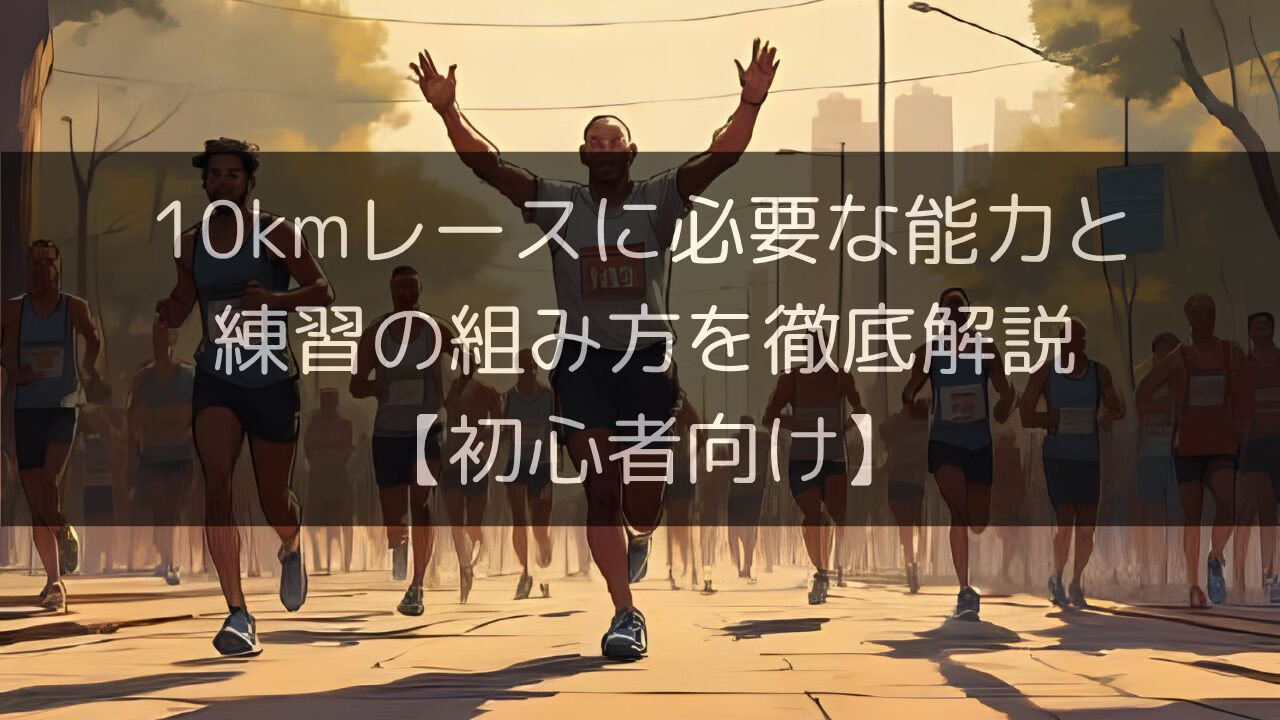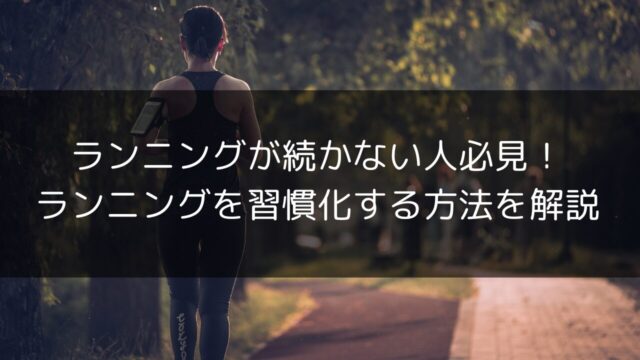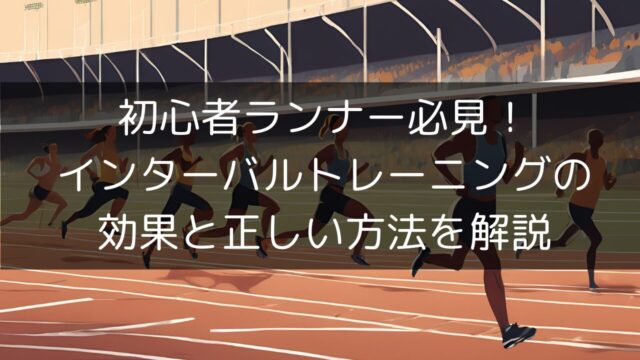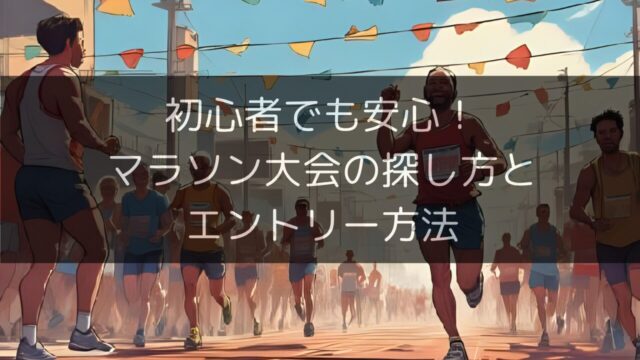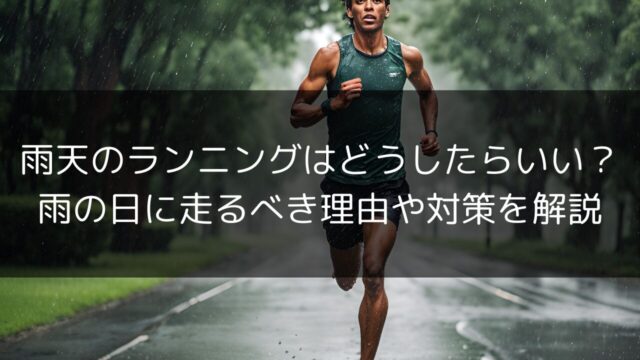10kmの大会に挑戦しようと考えている方は、初めてのチャレンジで完走を目指すランナーから、フルマラソンのスピード強化を狙う方まで、さまざまな目的を持っていることでしょう。
私自身もフルマラソンを主戦場にしていますが、スピードアップを図るため10kmレースに出場することがあります。
この記事では、10km大会に向けた練習メニューの組み方をお伝えしますので、何を優先して練習したら良いかわかるはずです。
10kmのレースに出るには?

マラソン大会では公道を走ることが多いですが、10kmの大会では陸上競技場で開催されることもあります。
市民ランナーの中には、陸上競技場で走ることに慣れていない方も多いかもしれません。400mトラックを何周も走ることに対して、「単調で飽きそう」と感じる方もいるでしょう。しかし、陸上競技場は走るために整備された地面であり、タイムが出やすいのも事実なんです。
大会を探すにはRUNNETなどのサイトがおすすめです。
RUNNETはこちらから➡️https://runnet.jp/
10kmのレースに必要な能力

10kmレースはスピードと持久力のバランスが重要な種目です。完走やタイム向上のために必要な能力は以下の通りです。
- 最大酸素摂取量(VO2max)
- 乳酸性閾値(LT値)
- 筋持久力
- ランニングエコノミー
- レースペース配分・感覚
- 精神力
最大酸素摂取量(VO2max)

VO2maxは、運動中に体内に取り込むことができる酸素の最大量を示す指標であり、運動時の全身持久力を表す重要な数値です。
10kmレース中の走行強度はVO2maxの90〜94%程度に達します。そのため、VO2maxが高いランナーほど速いタイムを記録しやすいです。
5kmや10kmのレースタイムはVO2maxの能力がダイレクトに反映され、VO2maxが高いほど競技成績が向上します。
鍛え方
- インターバル走:速いペースで走る「疾走区間」と、ジョグ等で体力を回復させる「休息区間」を交互に繰り返す
➡️インターバル走の詳しい説明はこちら - ペース走:レースペースに近い速度で、ペースを落とさないように一定時間走る
- ビルドアップ走:走り始めは余裕のあるゆっくりとしたペースでスタートし、一定の距離または時間ごとに段階的にペースを上げていく。最終的には自分にとってきついと感じるペースまで上げて走り切る
乳酸性閾値(LT値)
LT値が高いほど、乳酸が急激に蓄積し始めるペースの上限が上がり、より速いペースで長時間走っても疲労しにくくなります。
10kmレースでは、ほぼLT値付近のペースで走ることになるため、LT値の向上が記録アップに直結します。
LT値を高めるには、「LTペース」や「Tペース」と呼ばれる、20〜30分間維持できる強度での持続走(テンポ走/閾値走)が最も効果的です。
鍛え方
- テンポ走(閾値走/LT走):20〜30分間、LTペースで4〜8km程度走る。走り終えた時「あと1kmなら走れる」と思えるくらいが適切な強度
- インターバル:1〜3km×複数本をLTペースで、間に短めの休息(ジョグやウォーク)を挟む。1km×7〜10本、2km×3〜5本、3km×2〜3本が適切な距離。
- ビルドアップ走:徐々にペースを上げていき、最後にLTペースまで上げる。
筋持久力

ランニング動作は設置の繰り返しなので、脚の筋肉が長時間にわたって筋力を動かし続ける能力です。
筋持久力が不足していると、レース後半で脚が重くなり、ペースダウンしてしまいます。特に坂が多いような起伏のあるレースでは特に影響が多くなります。
また、効率的なフォームの維持にも筋持久力は重要です。
一般的に、同じ負荷をかけても心肺機能の方が先に向上しやすく、脚(筋持久力)がウィークポイントになりやすいと言われています。
鍛え方
- ロング走:レースペースよりも遅いペースで長い距離を走る
- 坂道走や起伏コースの活用:筋肉への負荷を高め、脚の筋持久力を効率よく鍛える
- 筋力トレーニング(スクワット、ランジなど):筋肉の耐久性とパワーを底上げ
ランニングエコノミー
ランニングエコノミーは、「一定の速度で走る際に消費する酸素量(エネルギー量)がどれだけ少ないか」を示す指標です。ランニングエコノミーが良いと走るのに必要なエネルギーが少なく、効率よく走れていることになります。
要するに「どれだけエネルギーを節約できるか」ということです。
例えば、同じ最大酸素摂取量(VO2max)を持つランナーでも、ランニングエコノミーが良い方が速く長く走れます。
- ランニングフォーム(ランニング時の上下の動きの大きさ等)
- 酸素の取り込み能力
- 適切なシューズかどうか
➡️シューズの選び方はこちら - レース環境(路面の硬さ、気温、天候)
レースペース配分・感覚

10kmレースでのペース感覚は、目標タイムに合わせた一定のペースを正確に把握し、無駄な力みやオーバーペースを防ぐために不可欠です。適切なペース配分ができないと、前半飛ばしすぎて後半失速したり、逆に遅すぎて記録を伸ばせなかったりします。
ペース感覚が身につくと、GPS時計を見なくても自分の走りのリズムや感覚でペースをコントロールできるようになる。イーブンペース(一定で同じペース)を維持することが、10kmのような距離では最も効率的かつラクに走れる方法とされています。
鍛え方
1kmごとにラップを計測できるコース(公園の周回路や陸上競技場など)で、目標ペースを正確に維持して走り体にペースを覚えさせる
精神力
意外かもしれませんが、精神力(メンタル)がパフォーマンスを大きく左右します。精神的に弱気になると本来の力を発揮できず、逆に精神力が強ければ想定以上の走りができることもあります。
特に10kmは「短いから最後まで全力」と思いがちですが、実際は後半にかけて肉体的・精神的な苦しさが増し、「もう止めたい」「ペースを落としたい」という誘惑と戦う場面が必ず訪れます。このとき、自分自身の限界を乗り越える力や、苦しさに耐えて粘る力が精神力です。
鍛え方
- 具体的な目標タイムや達成したいことを設定する
- 「自分ならできる」「ここまで頑張ってきた」など、自己肯定感を高める自己暗示
- 1kmごとや折り返しごとに小さな目標を作り、達成感を積み重ねる
- 自信がつくまで練習を繰り返す
- 緊張時には、深呼吸やリラックスできる音楽を活用して心を落ち着かせる
- レース経験を何度か積み、大会に慣れる
10km大会に向けた練習メニューの組み方

10kmのレースで目標タイムを達成するためには、効率的かつ継続的な練習が欠かせません。ここでは、10km練習メニューの組み方について解説していきます。
目標設定をする
練習を始める前に、明確な目標タイムを設定しましょう。
目標を具体化することで、練習の方向性が明確になり、効率が大幅に向上します。また、目標タイムに応じて必要な1kmあたりのペースを計算しましょう。
例
- 50分切り:5分/km以内
- 45分切り:4分30秒/km以内
- 40分切り:4分/km以内
練習頻度を決める
練習頻度は、個人のレベルや体力に応じて無理のない範囲で設定しましょう。
初心者の場合
週3回を目安に練習を始めましょう。まずはランニングを習慣化し、体力を徐々に向上させることを目指します。
中級者~上級者の場合
週4~7回の練習がおすすめです。上級者の中には毎日走る人も多いですが、けがのリスクを考慮し、適度に疲労を抜く日を設けることが大切です。
練習の強度は日によって変化をつけましょう。すべての練習を高強度で行うのではなく、ジョグやリカバリーランを取り入れることで、疲労を回復させながら継続的に練習を行えます。
最低でも週3回の練習を維持することが、体力向上と目標達成への近道です。
入れるべき練習内容
目標達成のためには自分の弱点を把握し、それに応じた練習メニューを計画することが重要です。具体的な弱点に対応する練習方法や、バランスの取れたトレーニングのポイントをご紹介します。
1. 自分の弱点を知る
最初に、自分の弱点を明確にしましょう。例えば、以下のようなポイントを振り返ってみてください
- レース終盤でペースが落ちる
- 坂道や起伏の多いコースで失速する
- レースペースが安定しない
- 長距離を走るときにフォームが崩れる
2. 弱点に応じた具体的な練習
弱点を克服するためには、目的に応じた練習を取り入れましょう。
- 筋持久力が弱い場合
坂道ダッシュや起伏を使ったランニング - ペースのムラがある場合
ペース走で一定のペースで走る感覚を体に染み込ませる - スピード不足の場合
インターバルトレーニングで全力の90%程度のペースで走る
3. 練習メニューのバランスを取る
特定の練習に偏るのは、思わぬ弱点を生む原因になります。例えば、スピード練習ばかりを行うと、筋持久力や心肺機能が十分に鍛えられない可能性があります。
ジョグを中心にバランスよく練習メニューを組んでいきましょう。
まとめ

10kmレースはスピードと持久力のバランスが求められる、非常に魅力的な種目です。この記事では、必要な能力や効果的なトレーニング方法、練習メニューの組み方について解説しました。
まずは自身の目標を設定し、それに応じた練習計画を立ててみてください。
10kmレースは、マラソンとはまた違う達成感や楽しさを味わえる距離です。ぜひこの記事を参考に練習を進め、次回のレースで自己ベストを更新を目指してみてください。