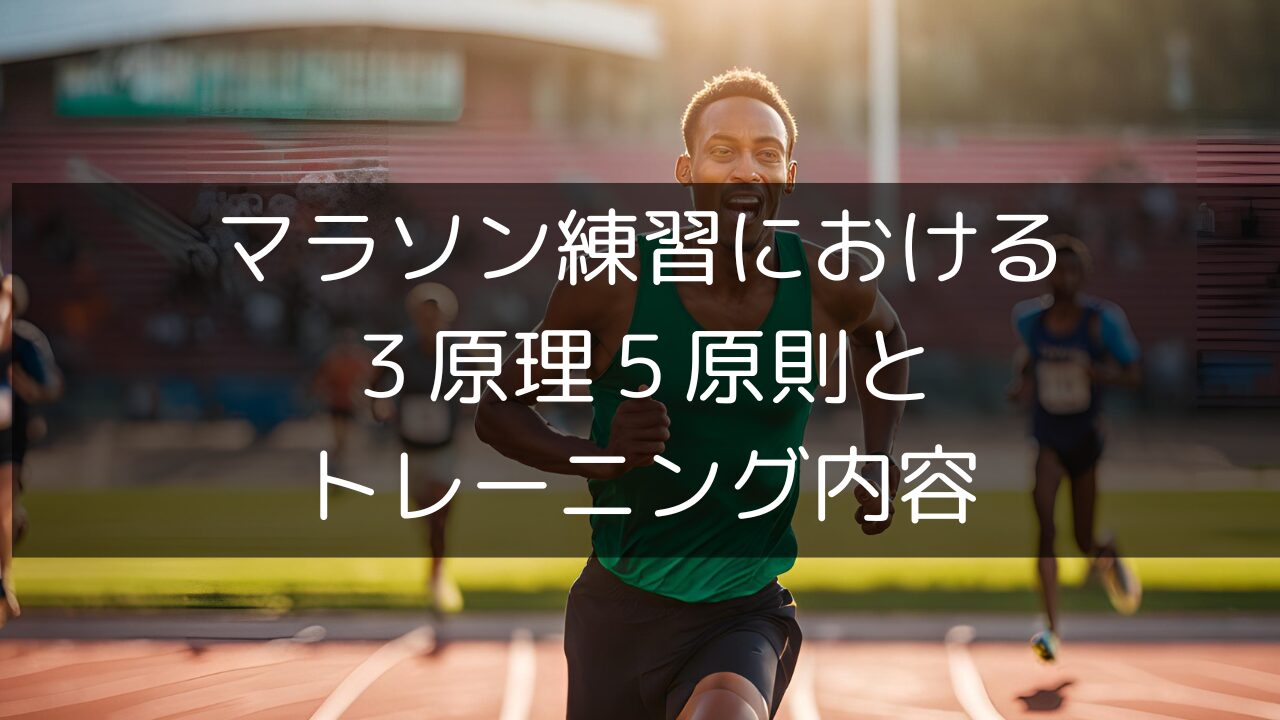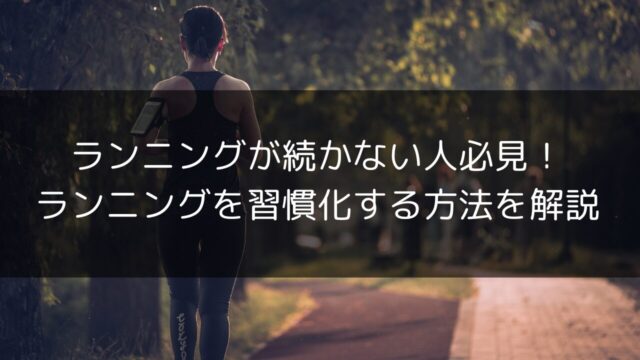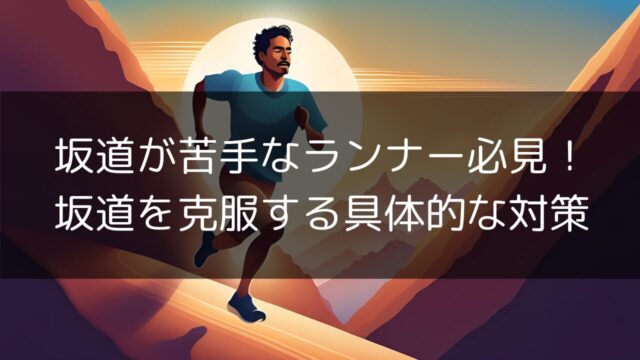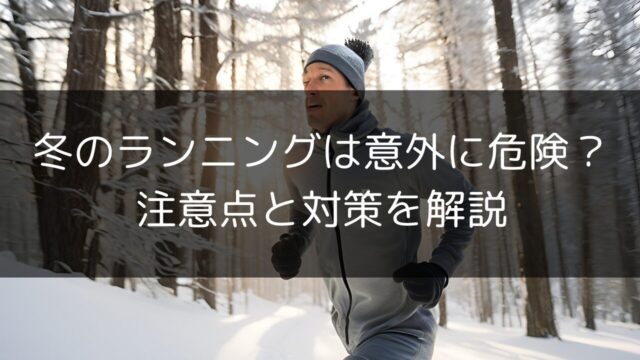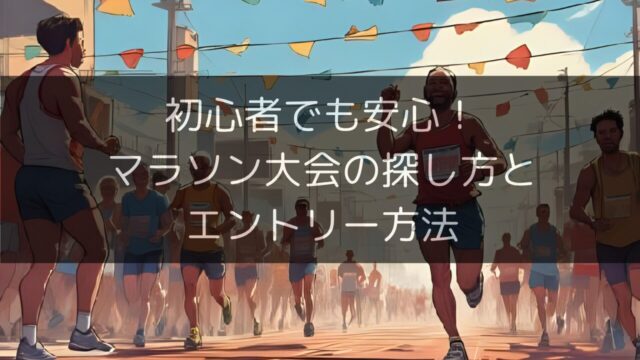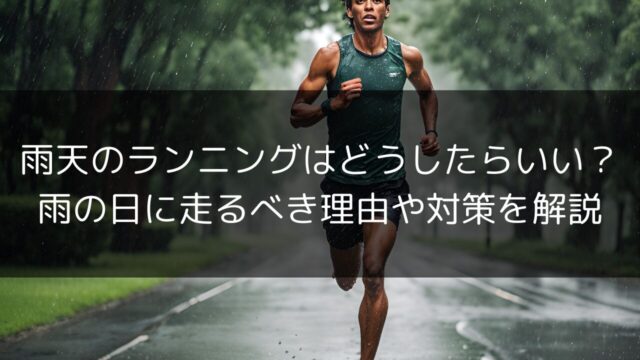マラソンの練習をしても、タイムがなかなか伸びないと悩んだことはありませんか?速くならないと、自分には走る才能ないのかな…と思ってしまうかもしれません。
でも、マラソンは生まれもった才能よりも、正しい練習が必要なスポーツです。
トレーニングには原理原則があり、3原理5原則と言われています。この原理原則を元に練習メニューを組めば、今よりも必ず成長出来ます。
そして、それぞれのメニューにおける効果を知っておくことも重要です。インターバル走やペース走では、行う目的も変わってきます。
目的意識をもって練習することで、練習効果を最大限に引き出せます。
- トレーニングの3原理5原則をマラソンに当てはめるとどうなるか
- マラソンのトレーニングの目的や効果
トレーニングの3原理5原則

トレーニングには、どのスポーツにも当てはまる原理原則があります。研究者によって若干の違いはありますが、トレーニングにおける3つの原理・5つの原則が有名です。
3つの原理とは
「過負荷の原理」「可逆性の原理」「特異性の原理」のことで、
5つの原則は
「全面性の原則」「意識性の原則」「漸進性の原則」「反復性の原則」「個別性の原則」のことです。
以下に詳細を説明していきます。
3つの原理
①過負荷の原理
今のレベルよりもより高い強度の練習を乗り越えることで、運動機能が向上していくこという考え方です。
マラソン練習においては楽な練習ばかりしていてもダメで、ある程度「キツイ」と感じる負荷をかけていくことが必要です。ジョギングだけでなく、インターバル走やペース走などの練習を取り入れましょう。
ただ、負荷を上げるということは怪我のリスクは上がるため、徐々に負荷を上げていくことが大切です。
②可逆性の原理
練習によって得られた能力の向上が、一定期間練習をしないことによって低下するという考え方です。当たり前ですが、運動機能は上がるだけでなく下がることもあるのです。
数日走るのをやめてしまうだけで、筋力や肺機能が低下してしまいます。怪我や天候で仕方がない場合もあるかもしれませんが、できるだけ練習を継続していきましょう。
習慣化については以下の記事も参考にしてください。
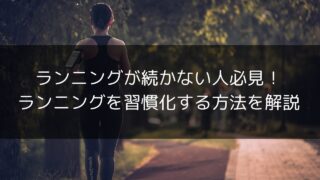
③特異性の原理
スポーツのそれぞれの種目に特化した練習をしないと、その競技能力は向上しないという考え方です。マラソンが速くなりたのに、水泳やウエイトトレーニングだけ行ってもいけません。
マラソンにおいての特異性とは、「レースペースで42km走る」ことです。レースペースよりも遅いペースで走っていても、マラソンでは結果が出ないかもしれません。
毎日でなくていいので、レースペースで走る練習を必ず行いましょう。
5つの原則
①全面性の原則
同一の箇所に過度に負担をかけるのではなく、体全体を鍛えていくという原則です。
マラソンではスピード練習と持久系の練習の両方が必要です。
また、走動作は足に負担が過度にかかってしまうので、腹筋運動などの補強運動も大切になってきます。
②意識性の原則
練習をするときに、目的やどのような効果を期待して行うのかを理解して、その目的を意識して行うことでより効果が高まるという原則です。
何気なく走るよりも、「今日は腕振りを意識しよう」「この練習はペースを落とさずに走り切るのが大切」など目的意識をもつことで、練習効果を最大化出来ます。
さらに練習の目的を意識することで、飽きずに練習を継続する効果もあります。
③漸進性(ぜんしんせい)の原則
トレーニングの強度を現在のレベルに応じて徐々に上げていくことで、能力が効率的に向上する原則です。
重要なことは「徐々に」上げていく点です。大幅に上げてしまうと怪我のリスクもありますし、きつ過ぎると継続が精神的にも負担が大きく出来ません。
その都度運動強度を見直しながら、練習の負荷を上げていきましょう。
④反復性の原則
トレーニングは長期間実施することにより、ようやく目にみえる大きな効果があらわれるという原則です。
マラソンにおいても、サブスリーなど大きな目標であれば数年かかると思っておいた方がいいでしょう。
長期的に練習を継続していきましょう。
⑤個別性の原則
個人の体力や技術レベルに合わせて、トレーニング内容を選ばなくてはならないという原則です。
レースの結果から、自分に足りない部分や苦手な部分を把握して練習を組みましょう。
有名なマラソンランナーの練習メニューをそのまま真似をしても意味がなく、自分に合った練習をしていきましょう。
ランニングのトレーニングメニュー

ここまでトレーニングにおける3原理5原則を解説してきました。
マラソン練習において必要な練習は、心肺機能や筋持久力を向上させる練習です。
以下どのような練習があるか紹介します。
ジョグ(ジョギング)
楽と感じるペースで長く走る練習。ランニング練習の基本であり、練習の大半を占めます。負荷が少ない分、フォームを意識したり、調子を確認しながら行いましょう。
ウォーミングアップやクールダウン、長い距離を走りたいとき、ポイント練習(負荷の強い練習)のつなぎとしても使用します。
インターバル走
速いペースで走る区間とジョグ区間を数本繰り返す練習。
速いペースで走る区間は、レースペースやそれ以上速いペースで行い動きを体に定着させる。距離は200m〜2000mで設定することが多い。
マラソン練習の中で、最もスピードを上げる練習であり、足にかかる負荷は大きいので怪我には十分注意する。
ビルドアップ走
決められた距離をスタートからゴールまで、徐々にスピードを上げていく練習。後半の疲れている場面でも、スピードを上げていくので筋持久力などが鍛えられます。
途中でペースが落ちないようにペースを設定する。
一人で行うには、精神的にキツかったり、ペースが安定しないのでランニング仲間がいれば一緒に行うのがオススメ。
ペース走
一定のペースを保って、比較的長い距離を走る練習。長い距離への対応、スピード持久力をつけることが目的で、一人でも行いやすい。
ペースはAT値(有酸素運動から無酸素運動に切り替わる運動強度)で本来は行いますが、AT値を正確に測定するには、特別な器具が必要になります。
理論上は「フルマラソンを走りきるのに、最も速いペース」がAT値となるので、フルマラソンの設定ペースから行ってみるのがオススメです。
距離走
一定のペースで20~40km程度走る練習。スタミナをつけることが目的。
フルマラソンの練習において、最も重要な練習でありトップランナーも必ず行なっている練習。
ペースは目的によって様々ですが、試合が近くなるとレースペースに徐々に近づけていくのが一般的。
レペティション
完全休養を挟み、全力で一定の距離を走る練習。短い距離を高強度のスピードで走り、一本一本しっかりと追い込む。心肺機能を追い込むことが出来るが、非常に負荷が強いので怪我には注意が必要。
陸上競技場など、スピードを出しても危なくない場所で行う。
ヒルトレーニング(坂道走)
傾斜地を全力で駆け上がり、下りはジョグでつなぐ練習。短時間で高負荷をかけることが出来るため、時間効率がいい。
坂道走は動きが大きくなり、ランニングフォームの修正にも繋がる。
時間のない市民ランナーにはオススメの練習。
流し(ウインドスプリント)
正しいフォームを意識して100m ~300mを、やや速めのスピードで走る。
ジョグの後など、フォームが小さくなった後に取り入れると動きが修正されて、翌日の練習につながる。
速いスピードで走るため、スピード練習の意味合いもある。
まとめ

トレーニングにおける3原理5原則と、マラソンのトレーニングについて解説してきました。
マラソンは正しい練習を行えば成果は出やすいので、トレーニング理論を理解して正しい練習を行っていきましょう。
せっかく練習をするのなら、効果を最大限引き出せるように試行錯誤しながらやっていきましょう。